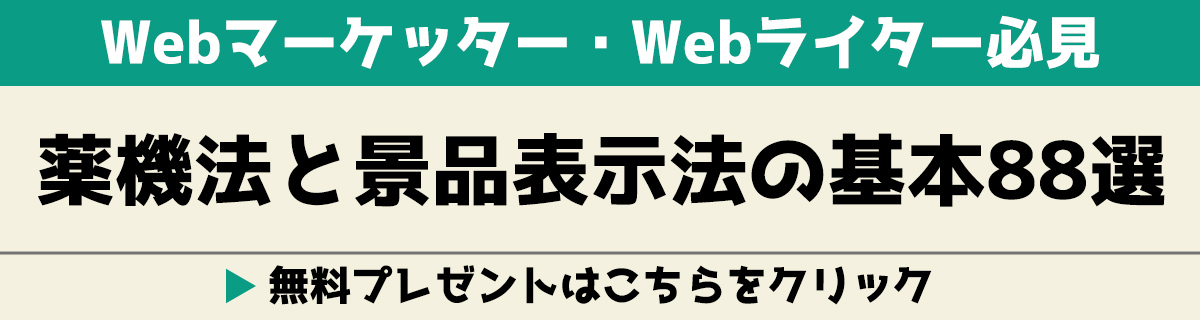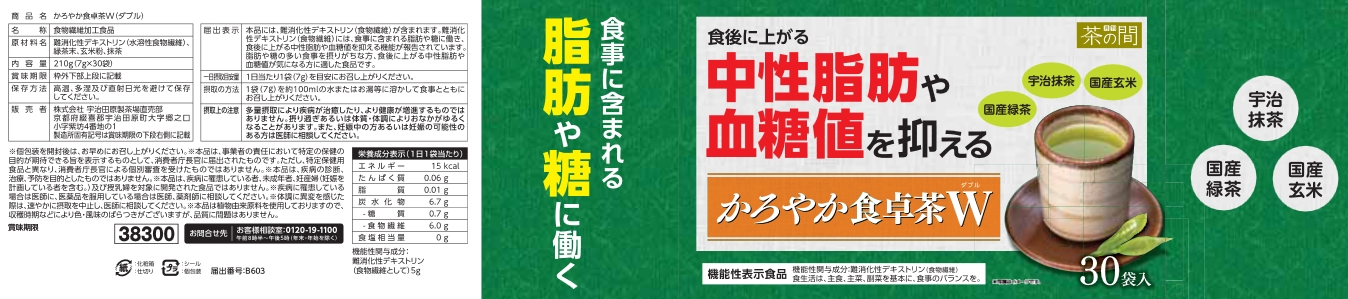| 届出番号 | C261 |
| 商品名 | こんにゃくゼリー マキベリー |
| 届出者名 | 雪国アグリ株式会社 |
| 届出日 | 2017/10/11 |
| 変更日 | 2019/04/15 |
| 撤回日 | 2019/09/27 |
| 販売中 | 販売休止中 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
| 表示しようとする機能性 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維として)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維として)はお腹の調子を整えることが報告されています。 |
| 当該製品が想定する主な対象者 | お腹の調子を整えたい20歳以上の方 |
| 一日当たりの摂取目安量 | 5個 |
| 一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量 | 機能性関与成分名:難消化性デキストリン(食物繊維として) 含有量:5g |
| 保存の方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けてください。 |
| 摂取の方法 | 良くかんで少しずつお召し上がりください。 |
| 摂取をする上での注意事項 | 本品は、多量摂取により疾患が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日当たりの摂取目安量を守ってください。一度に多量に摂ると体質によってお腹が緩くなる場合があります。 |
| 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項 | 無 |
| 消費者庁URL | https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc02/?recordSeq=41909270580301 |
安全性に関する基本情報
安全性の評価方法
■喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。
■既存情報による食経験の評価により、十分な安全性を確認している。
当該製品の安全性に関する届出者の評価
当該製品と同じ機能性関与成分を配合したこんにゃくゼリーを販売しております。2009年から販売され、約2千万食の販売実績があり、これら製品を摂取したことによる健康被害などの問題は報告されておりません。
また、国立健康・栄養研究所「健康食品」の素材情報データベースを調べたところ、健康被害情報はありませんでした。しかし、当該製品の一日当たりの摂取目安量である難消化性デキストリン(食物繊維として)5gの約7倍量に相当する量を摂取した場合には下痢症状を起こす可能性があることが報告されているため、「一度に多量に摂ると体質によってお腹が緩くなる場合があります。」を摂取上の注意として表示します。
機能性に関する基本情報
機能性の評価方法
■最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。
当該製品の機能性に関する届出者の評価
【標題】
難消化性デキストリンを用いた健常成人に対する整腸作用(便通改善作用)に関するシステマティックレビュー(メタアナリシス)
【目的】
水溶性食物繊維である難消化性デキストリンは、便通改善効果、血清脂質代謝改善効果、血糖調節効果などの生理機能を有することが確認されている。
今回、難消化性デキストリンが有する整腸作用(便通改善作用)について、健常成人あるいは便秘傾向の成人を対象としたランダム化比較試験のシステマティックレビューを行い、有効性を確認した。
【背景】
日本人の食事摂取基準(2015年版)によると、食物繊維の摂取基準は18歳以上の男女において、目標量が男性19~20g/日、女性17~18g/日と設定されているが、「平成24年国民健康・栄養調査報告」によると、20歳以上の1日当たりの食物繊維摂取量は平均14.8gとされており、食物繊維の摂取不足が推測される。
日本では、難消化性デキストリンは多くの特定保健用食品にも使用されており、平成27年9月4日時点で387品目の特定保健用食品に使用されている。そのうち、整腸作用を目的とした商品は181品目となっている。
そこで今回、水溶性食物繊維である難消化性デキストリンの整腸作用(便通改善作用)に関するシステマティックレビュー(メタアナリシス)を実施した。
【レビュー対象とした研究の特性】
文献検索のデータベースは、国内外の関連論文を網羅的に収集し、採用基準に基づき27の研究をシステマティックレビューに用いた。本研究レビューは届出者からの依頼を受けて、松谷化学工業株式会社が独立して検証した。
【主な結果】
本研究における難消化性デキストリン(食物繊維として)の1日摂取量は3.8~7.7gであり、最小摂取量3.8gの摂取によっても「排便回数」および「排便量」において対照群との有意差が認められた。
【科学的根拠の質】
今後の研究によっては、システマティックレビューの結果が変わる可能性はあるため、継続した調査が必要である。また、整腸作用は生活習慣も重要な要因であり、1つの食品だけを摂取すれば問題ないという考えではなく、食生活や運動などにも注意を払う必要がある。適切な整腸作用を継続するうえで必要な要素として、食事療法だけでなく、運動療法、その他生活習慣病などとの交絡因子の影響について、継続した研究が必要と考えられる。