ネット上で度々話題になるステルスマーケティング。SNSが盛んに使われるようになってより問題になるケースが増えてきています。
今回はステルスマーケティングの規制や事例などについて説明します。
⇒PDF無料プレゼント「薬機法OK・NG表現がわかる!薬事表現の具体例集148」
ステマ(ステルスマーケティング)とは?意味や定義
ステルスマーケティングはインターネット上では、「ステマ」と省略されてよく使われています。英語では、「Stealth Marketing」です。
ステルスマーケティングの意味は、消費者に広告であることを隠して、商品やサービスの宣伝をしたり、好意的な口コミを行ったりすることです。
景品表示法では「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」という言葉が使われています。
ステマ規制とは?
ステマ規制とは、消費者に広告であると明記せずに隠して行われた宣伝行為等を取り締まる法律で、2023年10月1日に施行されました。
ステマ規制は正式名称ではありません。消費者庁ではステルスマーケティングのことを「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」という名称で規制しています。
ステルスマーケティングは景品表示法第5条第3号に基づく指定告示として、規制されます。
前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
『「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準』
の消費者庁資料はこちらのページです。
※景品表示法第5条第3号に基づく指定告示には、他に「おとり広告に関する表示」などがあります。
ステマ規制の対象
ステマ規制の対象は、商品やサービスを提供する事業者です。
広告の依頼を受けたインフルエンサーや広告代理店等は、対象ではありません。
ステルスマーケティングの効果
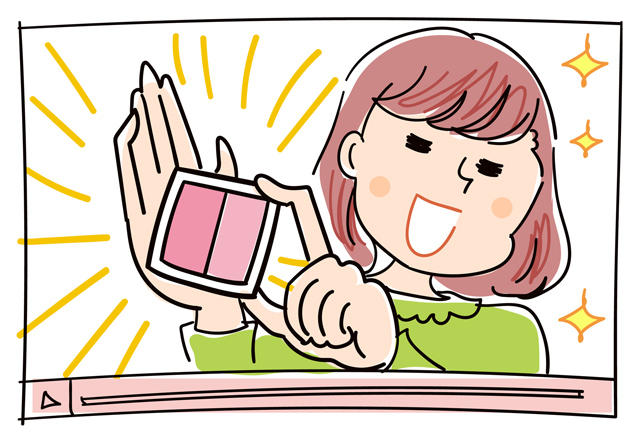
ステルスマーケティングは、人気のあるインフルエンサーや権威性の高い人が行えば、絶大な効果を及ぼします。インフルエンサーの影響力は大きく売上が一気に伸びる事例も多くあります。
ステルスマーケティングでは、「ウィンザー効果」が働いています。
ウィンザー効果とは、販売者ではない第三者の口コミのほうが信頼性が増すという心理現象です。
そして、さらにその第三者の影響力や信頼性が強い場合、その人の信頼性が商品にも移ります。好きな芸能人が「これめちゃくちゃ良いからおすすめ」と紹介していたら使ってみたくなる人も多いでしょう。
ステルスマーケティングは違法?なぜ悪い?
ステルスマーケティングは、規制により違法となります。アメリカ・ドイツ・フランス・イギリスなどの先進国では以前から違法とされており、日本でも問題が大きくなってきたため、規制が設けられました。
規制が設けられる背景は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるためです。
ステルスマーケティングによる表示は、一般消費者が表示全体から抱く印象・認識と、実際のものに乖離を生じさせます。
例えば、SNSで大好きなインフルエンサーがおすすめの商品ですと広告であることを隠して紹介していた場合や、レビューサイトで事業者の従業員が一般ユーザーを装い、高評価の点数および絶賛するコメントを投稿していた場合などは、誤認が生じる可能性は高いでしょう。
ステルスマーケティングの種類
ステルスマーケティングは大きく分けて以下の2つの方法で行われます。
なりすまし型
なりすまし型とは、企業の内部の人間や関係者が、関係のない第三者を装い、口コミを行うことです。
例えば、食べログやGoogleMapの店舗情報ページに関係者が書き込む行為がこれに当たります。
食べログやGoogleMapは、ユーザーがたくさん見ていて消費活動を行う時の参考にしています。そのため、その口コミや評価が大きく売上に関係します。よって、なりすましによって口コミが行われるのです。
利益提供型
利益提供型とは、インフルエンサーや著名人、サイト運営者などに報酬を渡して、高評価の口コミをしてもらうことです。
例えば、Youtuberが「この商品を普段から使っていてお気に入り」と紹介したものが実は普段は使っておらず、報酬をもらって紹介しただけだった、というような場合です。
ステルスマーケティングのメリット
ステルスマーケティングは、低価格ですぐに取り組むことができますし、ポータルサイトの口コミ、インフルエンサーの口コミなど、どちらでも大きく売上に貢献する可能性があります。
そのため、事業者や広告代理店など、関係者が行う事例が後を絶ちません。
ステルスマーケティングの判断基準
ステルスマーケティングの判断基準としては、以下を参考にしてください。
| ステマになる | ステマではない | |
| 事業者の表示 | 「広告」「PR」など事業者の表示であることを書いていない、または不明瞭 | 広告であることが明瞭または社会通念上明らか |
| 事業者の関与 | 事業者が第三者の表示内容の決定に関与している | 第三者が自主的に表示している |
ステルスマーケティングの規制対象になる場合(1)
事業者が表示内容の決定に関与したと認められる場合には規制対象になるおそれがあります。
関与したとされる場合とされない場合については以下となっています。
関与したとされる場合
(1)事業者が自ら行う表示について
事業者が自ら表示しているにもかかわらず第三者が表示しているかのように誤認させる表示(例えば、従業員が行った場合)
(2)事業者が第三者をして行わせる表示について
事業者が第三者をして行わせる表示の具体例は以下です。
−事業者が第三者に対して、当該第三者のSNS上に当該事業者の商品又は役務に係る表示をさせる場合。
−ECサイトに出店する事業者が、いわゆるブローカー(不正レビュー等を募集する者)や商品購入者に依頼して、ECサイトのレビューを通じて表示させる場合。
−事業者がアフィリエイトプログラムを用いた表示を行う際に、アフィリエイターに委託して、当該事業者の商品又は役務について表示させる場合。
−事業者が他の事業者に依頼して、プラットフォーム上の口コミ投稿を通じて、競合事業者の商品又は役務について、自らの商品又は役務と比較した、低い評価を表示させる場合
関与したとされない場合
(1)第三者の自主的な意思による表示と客観的に認められる場合は、事業者の表示とはならない
自主的な意思による表示と客観的に認められる場合の具体例は以下です。
−第三者の自主的な意思に基づき、SNS等へ当該商品又は当該役務に関する表示を行う場合。
−アフィリエイターの表示であっても、事業者と当該表示に係る情報のやり取りが直接又は間接的に一切行われていない場合。
−ECサイトに出店する事業者の商品を購入する第三者が、自らの自主的な意思に基づき、ECサイトのレビュー機能を通じて、商品等の表示を行う場合
−ECサイトに出店する事業者が購入者に対し、ECサイトのレビュー機能による投稿に対する謝礼として、次回割引クーポン等を配布する場合であっても、事業者と購入者との間で、購入者の投稿(表示)内容について一切の情報のやり取りが行われておらず、購入者が自らの自主的な意思に基づき投稿(表示)したと客観的に認められる場合
−第三者が、事業者がSNS上で行うキャンペーンや懸賞に応募するために、第三者の自主的な意思に基づきSNS等に表示を行う場合
−事業者が自社のウェブサイトにおいて、第三者が行う表示を利用する場合であっても、当該表示を恣意的に抽出せず、また、第三者の表示内容に変更を加えることなく、そのまま引用する場合
−事業者が不特定の第三者に対して、試供品等の配布を行った結果、これらを受けた不特定の第三者が自主的な意思に基づき表示を行う場合
−事業者が特定の第三者(例えば、会員制サービスの会員)に対して、試供品等の配布を行った結果、これらを受けた特定の第三者が自主的な意思に基づき表示を行う場合
−事業者が表示内容を決定できる程度の関係性にない第三者に対し、表示を行わせることを目的としていない商品又は役務の提供(例えば、単なるプレゼント)をした結果、当該第三者が自主的な意思に基づき表示を行う場合
(2)新聞・雑誌発行、放送等を業とする媒体事業者が事業者の指示に左右されず、自主的な意思で企画、編集、制作した表示については、事業者の表示とはならない
ステルスマーケティングの規制対象になる場合(2)
一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっていない場合は、規制対象になるおそれがあります。
(1)当該表示が記載されていないものについて
−当該事業者の当該表示であることが全く記載されていない場合
−事業者がアフィリエイトプログラムを用いた表示を行う際に、アフィリエイトサイトに当該事業者の表示であることを記載していない場合
(2)当該表示が不明瞭な方法で記載されているものについて
−事業者の表示である旨について、部分的な表示しかしていない場合
−文中に「広告」と記載しているにもかかわらず、他の箇所で「これは第三者として感想を記載しています。」と記載し、事業者の表示であるかどうかが分かりにくい表示をする場合
−動画で事業者の表示を行う際に、一般消費者が認識できないほど短い時間において当該表示をする場合
−一般消費者が事業者の表示であることを認識できない文言を使用する場合
−事業者の表示であることを一般消費者が視認しにくい表示の末尾の位置に表示する場合
−事業者の表示である旨を周囲の文字と比較して小さく表示する場合
−事業者の表示である旨を、文章で表示しているものの、一般消費者が認識しにくいような表示の場合(例えば、長文表示、小さい文字の表示、他の文字より薄い色の表示など)
−事業者の表示であることを他の情報に紛れ込ませる場合(例えば、SNSの投稿において、大量のハッシュタグの記載の中に事業者の表示であることを埋もれさせる場合)
金銭なしでもステマになる?
金銭を受け取っていない人の投稿でもステマになるのかどうかですが、事業者の関与は金銭以外も含まれることが運用基準に明記されています。
事業者が第三者の表示に対して支払う対価については、金銭又は物品に限らず、その他の経済上の利益(例えば、イベント招待等)など、対価性を有する一切のものが含まれる。
ステマ規制で口コミ投稿やレビューは違法?
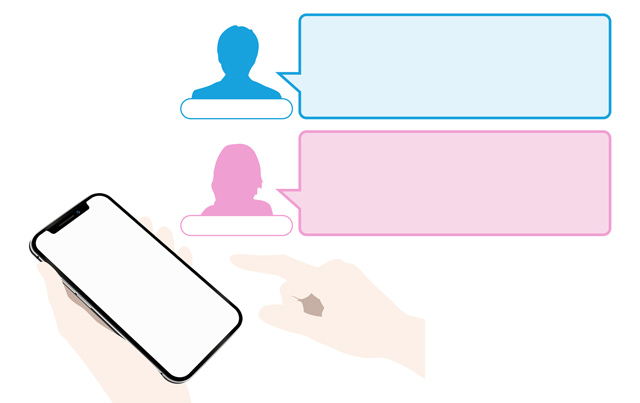
ステマ規制によって、
「お店の関係者がGoogleで高評価を行う」
「お金を払って良い評価を書いてもらう」
「自作自演で通販サイトで高評価レビューをする」
のような行為は、規制対象となります。
金銭や経済上の利益を与える代わりに口コミを投稿してもらうキャンペーンには規制が及ぶ可能性があります。
ステマ規制で過去の投稿は対象になる?
ステマ規制では、2023年10月1日の施行開始前に投稿された、過去の投稿や過去の動画も、閲覧可能な状態になっていれば、対象になります。
そのため、以前にステマを行っていて投稿がまだ残っている場合は削除したほうがいいでしょう。
ステマ規制を防ぐ表示
ステマ規制を防ぐためには、一般消費者が事業者の表示であることが分かる状態にする必要があります。
(1)事業者の表示であることが明瞭となっている
例えば、以下のような方法があります。
−「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」といった文言による表示を行う
場合。
−「A社から商品の提供を受けて投稿している」といったような文章による表示を行う場合
(2)一般消費者にとって事業者の表示であることが社会通念上明らかである
例えば、以下のような場合があります。
−CMのように広告と番組が切り離されている表示、映画等におけるエンドロール等の表示、新聞紙の広告欄のように「広告」等と記載されている表示、商品又は役務の紹介自体が目的である雑誌その他の出版物における表示を行う場合
−事業者自身のウェブサイトにおける表示、事業者自身のSNSのアカウントを通じた表示を行う場合
ステマ規制に違反した場合の罰則
ステマ規制に違反した場合は、再発防止を求める措置命令が消費者庁から出され、事業者名が公表されます。
措置命令に従わなかった場合には、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、またはそれらの併科となります。さらに、法人も最大3億円が科される可能性があります。
また、ステマ投稿が優良誤認や有利誤認の内容だった場合には、課徴金の対象となります。
SNSプラットフォーマーの対応
X(旧Twitter)
日本の規制が考慮された対応かは分かりませんが、X(旧Twitter)は、2023年1月25日(アメリカ時間)、有料パートナーシップポリシーを改訂し、報酬を受け取っていたり、広告とみなされたりするような内容を投稿する場合には、「#ad」などの記載をするように義務付けました。
<有料パートナーシップの具体例>
・金銭や贈り物の受け取り
・ブランド大使契約
・アフィリエイトリンク、利益につながる可能性のあるリンク
ステルスマーケティングが問題となった事例4個
1. バストアップサプリ事件
2021年11月9日にバストアップサプリに対して景品表示法違反の措置命令が出されました。
その対象の表示内容の中には、インスタでのステマ投稿が含まれており、ステマに対する措置命令は初でした。
2. ペニーオークション詐欺事件
2012年のペニーオークション詐欺事件では、ペニーオークションというその当時流行していたサービスの詐欺行為自体の問題性や話題性が高かったため、それをステルスマーケティングで宣伝していた芸能人も追及され、大問題となりました。
ペニーオークションとは、入札毎に低額の手数料がかかるオークションのことです。
ペニーオークション詐欺事件では、架空会員の自動ボットが金額を釣り上げ、超高額になるまで落札できないという仕組みになっていました。
そして、それをブログで「落札しました」などと嘘の宣伝をしていた芸能人も事情聴取を受ける事態となりました。
3. 食べログ事件
2012年、飲食店に良い口コミを書いて評価を上げるかわりに金銭を受け取る会社が39社いたことが明らかになり、問題となりました。
食べログでは、その店の関係者ではない利用者の口コミを売りとしているからです。
食べログを運営するカカクコムが関わっているわけではありませんでしたが、その後も何度も食べログではこのようなステマ疑惑で炎上が起こっています。
4. 女子アナのステマ疑惑
2021年に女子アナのステマ疑惑が問題となりました。複数の女子アナが広告とは明示せずに、無料施術を受けて美容院を自身のインスタグラムで紹介したためです。
芸能人や著名人が、宣伝を行う企業との関係性を明示せずに、金銭などの利益を得た上で、紹介する行為が問題となりました。
⇒PDF無料プレゼント「薬事法OK・NG表現がわかる!薬事表現の具体例集148」
まとめ
過去を振り返るとステルスマーケティングは10年以上続く問題となっています。今はSNSが発達して、これまでは一般人だった個人がメディアとなり、情報発信するケースが増えています。規模の大小はあれ、そこで商品を宣伝して金銭を受け取ることも多数あります。
企業だけでなく個人も情報発信する人は、ステマがどんなものなのか正確に把握してステマを行わないようにしましょう。












コメント